「心とは何か」 たぶん、「人には心がある」と信じている人は 多いだろうと思います。
ですが、改まって「心とは何?」と質問されると なかなかうまく答えられないと思います。
なぜなら、「心」は、実体のないただの概念だからです。
ブログ「読むカウンセリング」でも紹介したことがありますが、次の公案(禅の修行で活用される短いお話)も、同じようなことを言っているのだと思います。
【達磨安心】 雪の降りしきる極寒の日、壁に向かい続ける達磨をひとりの男が訪ねてきた。 名は神光。四書五経の万巻を読み尽くしていた。 彼は、膝まで積もった雪の中で問うた。 「心が不安でたまらないのです。先生、この苦悩を取り去って下さい」 「その不安でたまらない心というのを、ここに出してみろ。安心せしめてやる」 「・・・・・出そうとしても出せません。心にはかたちがないのです」 「それがわかれば安心したはずだ。かたちがないものに悩みがあるはずもない」 神光は、達磨から慧可という名前を与えられ弟子となり、やがて第2代の祖となった。
禅の本―無と空の境地に遊ぶ悟りの世界 (NEW SIGHT MOOK Books Esoterica 3)
- 出版社/メーカー: 学研マーケティング
- 発売日: 1993/04
- メディア: ムック
このように、心は、
- 「それがある」と思えば存在する
- 「それはない」と思えば存在しない
という性質のものなのです。 普段の実生活を考えてみて下さい。
たぶん、普通の生活をしているときには、 「自分」や「自己」を意識することは、たまにあると思いますが、 「心」を意識することは、ほとんどないと思います。
どのような時に、『心』を意識するのでしょう? それは、感情が生じたときです。
特に、ネガティブ(不快)系の感情を感じたとき (例えば、つらい、悲しい、苦しい・・・) 人は「心」を意識しやすいところがあります。
今回の説明では、感情を否定しているのではありません。 長くなるので、詳しく説明しませんが、
- 感情を心のせいにして、放置してしまうことが良くない
ということを説明しようとしています。
それぞれの人が、それぞれの時に、 様々な感情を感じるのは、当たり前のことです。
(注)これはあくまでも、感情が妥当だと言っています。その感情によって導き出した解決策が正当化できると言っているのではありません。
その感情を、心のせいにして、放置してしまうから 「心が苦しい」という思いの中に落ち込んで、抜け出せなくなってしまうのです。
自分に感情が生じているときには、慌てて何か行動を起こす前に、誰かにそばに居てもらい
- 悲しいときは、自分が悲しいことに気づき、しっかりと悲しむ
- 苦しいときは、自分が苦しいことに気づき、しっかりと苦しがる
極論すれば、ネガティブな感情は、 誰かにそばに居てもらって、すっきりするまで泣くことができれば、浄化することができます。
更に、安心な気持ちを取り戻し、一歩踏み出す勇気を手に入れることさえできるのです。
以前、ピュアハート・カウンセリングのホームページの心理百科事典に「恋愛依存」の説明を投稿しました。
そこで、恋愛は心の苦しさのワイルド・カードといった説明をしました。
恋愛にからめれば、心の苦しさを説明できてしまうからです。
実は、恋愛よりも強力なワイルド・カードがあるのです。 私は、これまで、心の苦しさを
- 人には、心がある
- 苦しさは、心が感じる
という前提で説明をしてきました。
しかし、実は、『心』という概念こそが、自分自身の苦しさの原因を曖昧にし、苦しいことの責任なら何でも押しつけることが出来るワイルド・カードなのです。
少し乱暴な言い方をすると、
- 「心が苦しい」と考えるのは、『心依存』という状態
と言うことができるのです。
- 眠いときは寝る
- 疲れたときは休む
- おなかがすいたらご飯を食べる
- 呼吸が浅く、息苦しい
- 尿意を催したらトイレに行く
- ガスがたまったら、おならをする
- 楽しいときは楽しむ
- つまらないときは、つまらないと感じる自分自身に優しくする
- 悲しいときは、悲しいと感じる自分自身に優しくする
- 怒っているときは、怒っている自分自身に優しくする
このように、苦しさの解決方法は、心理的な事ばかりではありません。
しかし、『心依存』的な状態になってしまうと、 「苦しさ」なら、何でもかんでも「心の苦しさ」と解釈してしまい、 本当の欲求を満たせなくなってしまうのです。
この状態に陥ったときに、その解決策として、 習慣的に「ある特定の行動」を選んでしまうことを、 一般的に、依存症と呼んでいます。
ですから、苦しさが解決できなくなってしまっているとき 心にばかり意識を集中させずに、 自分に生じているいろいろな感覚に気づいてあげることが大切です。
赤ちゃんが泣いたとき、 お腹がすいたのか、オムツが濡れたのか、機嫌が悪いのか・・・ ということを何度も何度も確認しました。
確認を3巡ぐらいして、ようやく、ミルクを飲んで寝てくれた、 なんてこともありました。
「心の苦しさ」という考え方に意識が向いているときは、 赤ちゃんが泣いたときの対応のことを思い出してみて下さい。
そのようなチェックを繰り返しているうちに、 自分の感覚に気づき、丁寧に扱えるようになると ずいぶんと気持ちが楽になると思います。
心の何かを解決しなくても、心の苦しさからが解放されることさえあります。
(このあたりの概要は、「心の解釈(第1巻)『心の苦しさの解釈』」で詳しく説明しています。)
そして、最後に残るのが、次の2つです。
- 条件反射を起こさせるために生じる感覚
- 現代社会独特の一般常識が引き起こす苦しさ
条件反射を身につけなければならない根本的な理由については、「心の解釈(第2巻)『心理カウンセリング解釈』」で、説明しています。
また、「現代社会独特の一般常識」に関連したことは、カテゴリー「これからの社会」で、少しずつ説明していきます。
ちなみに、禅の公案に興味のある方には「無門関」という本がオススメです。







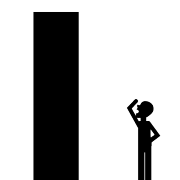














コメント