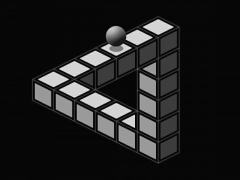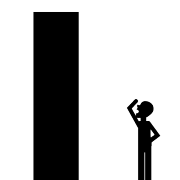トピックス
トピックス 04. 私たちの心の中に存在する『ある基準』について

読むカウンセリング【No.0003】 2005/12/12
こんにちは、「ピュアハートカウンセリング」カウンセラーの田中順平です。
今回は、言葉の説明というよりは、概念的なことを説明をさせて頂きたいと思います。
今回のメルマガの内容は大きく「1.説明」と「2.自分に気付く為のヒント」という2つの部分に分かれています。
私たちの心の中に存在する『ある基準』について
『ある基準』と書くと、問題となる特定の基準があるかもしれないと期待される方もいらっしゃるかも知れません。
でも、ここでいう『ある基準』とは個人ごとに異なる不特定の基準を指しています。
「車は左側通行」というように、社会的な混乱を避けるために、国家が法律として基準を統一したものもありますが、現代の日本社会においては、法律はあくまでも、最小限の基準が定められているだけで、少なくとも国家の統制からは、かなり自由なところで生活する事ができているといえるように思います。
このように、本来、比較的自由なはずなのに、不自由さを感じてしまうことがある理由の一つについてご説明をするのが今回のメルマガの目的です。
1.説明
前置きが長くなってしまいましたが、この『基準』ということについて、次の例を使いながらご説明していきます。
【例】
- 食事中にテレビを見てはいけない
- 食事中にテレビを見ても良い
日常生活の中で、例えば、「食事中のテレビ」ということをテーマにして議論を始めたとすると、「テレビを見る派」と「テレビを見ない派」に対立してしまったり、どちらか一方を結論とする為の話し合いになってしまったりしがちなところがあるように感じています。
つまり、基準についての認識を曖昧にしたまま、基準によって2つに分割された結果の方ばかりに意識が向いてしまうところがあるように感じています。
そんな議論の中で、『食事中のテレビ』といった基準が無い人に、「食事中にテレビを見ても良いと思う?」と問うと、恐らく、一般論であれば、「どちらでも構わない」と答えるのではないかと思います。
また、その人の食事中の様子を観察してみると、「テレビを見たい時は見ているし、見る必要の無いときは見ていない」といった行動をしているだけで、『食事中のテレビの是非』なんて事は、一切意識していないということが理解できるだろうと思います。
そして、観察者がそのように理解できたとしても、その理解は基準を持った人の理解に過ぎず、基準を持たない人は、そんな事とは無縁の世界で生きているわけです。
基準を持った人には、基準を持たない人の行動は、首尾一貫しない理解しがたい行動のように感じられるかもしれません。
しかし、基準を持たない人は、基準に縛られることが無い為に、その時々に把握した気持ちや状況に臨機応変に適応しながら行動することが出来るのです。
「食事中にテレビを見ても良い/見てはいけない」ということを分け隔てる基準を持ってしまっていると、本人は意識していなくても、どうしても、どちらかの判断をしなければならない心境に陥ってしまうだろうと思います。
また、基準に意識が集中する為、その時々の状況(条件や、自分や相手の気持ち)の違いに気付き難くなってしまいます。
その結果、状況よりも、基準の方を優先させてしまう為に、自分自身、時には、相手までをも、不自由な感覚に追い込んでしまうのではないかと思います。
逆に、この自分の気持ちに臨機応変に対応できることが、自由な感覚や『生き易さ』につながっていくのではないかと思います。
そして、その為には、自分の中に基準があることに気付き、そこから自由になる必要があるのです。
【まとめ】
もし、これから先の生活で『生き難さ』のようなものをを感じてしまったら、
- なぜ、テレビを見てはいけないのか?
- なぜ、テレビを見ても良いのか?
などと基準によって分けられる各々の定義について思考を巡らせるのではなく、自分の中の基準の有無を確認し、もし、基準がありそうなら
■そもそも、なぜ、自分の中にこの基準が存在しなければならないのだろうか?
と、自分の背景に意識を向けてみると、自分自身の本当の気持ちを理解する事を助けてくれるかもしれません。
2.自分に気付く為のヒント
1.反面教師
『反面教師』という言葉があります。もし、相手の許せないところを反面教師としていたり、緩やかに思っているというよりは、頑なに守っている信念がある時は、何らかの『基準』の存在を疑ってみる余地はあるかもしれません。
【例】
・人を傷つけたくない
・人に優しくしたい
・相手の気持ちを大切にしたい
・人を責めたくない
・相手の意見をしっかり聞きたい
などなど・・・
「父親(母親)のようになりたくない」と意識して頑張っているのに、気が付いたら、父親(母親)のようになっていたというような話をしばしば耳にする事があるかもしれません。
普通に考えれば、そうならないように努力しているのだから、そうなるはずはありません。ですが、『基準』が引き継がれてしまったと考えてみると、そうなってしまう事を理解できるかもしれません。
2.優柔不断
一概には言えませんが、「あの人は、毎回言っていることが違う」といった不満を感じてしまうとき、自分の中にもしかしたら、ある種の基準が存在している事を疑ってみる必要があるかもしれません。
そして、基準のどちら側が良いかという議論をするのではなく、その時々に相手が把握している状況を理解しようとすると、今まで気付かなかった色々な事に気付き始めるきっかけになるかもしれません。
そして、新しい気付きは、自分の中の基準から、自分自身を解放することを、きっと手伝ってくれると信じています。
3.他者への影響
自分の中に『基準』があると、自分自身をその基準で統制しようとしてしまいます。
それは本人も意識していることは多いかもしれません。
しかし、その基準が他の人にまで及んでしまっているかもしれないということを、意識していることは少ないような気がしています。
自分を統制するために、自分の置かれている環境や空間を統制しなければならない心境に追い込まれてしまうことも多いと思います。
例えば、食事中、「テレビを見ない派」の人が、テレビを消したい衝動に駆られるのは、そんな心理の表れかもしれません。
そして、環境を自分の基準で統制した結果、統制された環境によって、間接的に、そこに属する他の人を統制してしまうことがあるのです。
簡単に書くと、例えば、「人に優しくしたい」という思いがあまりにも強すぎると、本人にそのようなつもりは無くても、周りにいる人達を「優しくしなければならない」と感じる状況に追い込んでしまうかもしれないということです。
メルマガ編集後記【No.0003】
何かに深く悩んでいて、色々な気持ちを整理しながら、何かを隔てる基準について色々と考えていく中で、悩みからの出口が近づいてくると、何らかの基準を設けて
■ 『悩んでいる』 <--> 『悩んでいない』
という区別をしていることに気付くかも知れません。
ここのところの微妙なニュアンスを、簡単な文章でお伝えするのは難しいのですが、『自分は、悩んでいない状態ではない』と思うから、悩んでいる状態になってしまいます。
『悩み』というところから解放された自由な自分になる(戻る)ということは、『悩んでいる状態』と『悩んでいない状態』という区別が取り払われて、それらが一つになるということなのかもしれません。
よく分からないかもしれませんが、何かを感じて頂ければと思います。
(機会があれば、もう少し、詳しく説明してみたいと思います。)