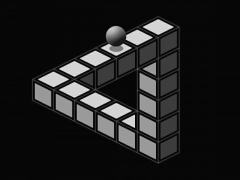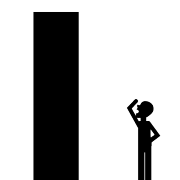 トピックス
トピックス 13. 『楽』になっても良いんです

読むカウンセリング【No.0012】 2007/08/14
気まぐれでなかなか発行されないメルマガなので、前回から約1ヶ月での発行でちょっと、ビックリされたかもしれませんね。(苦笑)
「楽になるって逃げることにはなりませんか?」
最近、そんな質問に繰り返し出合ったことに刺激されて、ちょっと、文章を書いてみたくなりました。何かを感じて頂けることを願っています。
『楽』になっても良いんです
何か困難な課題に出くわして、それに対処しているとき
■この対処は「課題から逃げている」のだろうか? それとも、「課題と向き合っている(逃げていない)」のだろうか?
などと考えることがあるかもしれません。
そして、そのように考えるときは、
■できることなら『逃げずに向き合う』という方向性で解決したい
と、きっと、多くの人が望んでいると思います。
単純に考えると、目の前に課題があれば、それを解決さえすればそれで良いはずです。
しかし、悩み込む傾向がある人は、「逃げずに向き合っているだろうか」ということが、とても気になってしまうようなのです。
そして、それが気になってしまう感覚によって、心の苦しみから抜け出せなくなっているところがあるように思いますので、今回は、このことについて説明したいと思います。
1. 何から逃げるのか?
どうして、その課題をクリアすることよりも、『逃げている』『逃げずに向き合っている』ということの方が気になるようになってしまうのでしょうか?
それを理解するために、まず、『逃げる』ということを考えてみたいと思います。
【例】
例えば、人前で話すことがすごく苦手な人が、ある人から「もし、良かったら、君のその素晴らしい経験を、1000人の前で1時間程度話して欲しい」と依頼されたとします。
これは、客観的に見れば、その人にとってまたとないチャンスで、本人もそうだと思っています。
しかし、そんな大勢の前で、しかも、1時間も話をするなんてとてもできないと、すごく不安で嫌な気持ちになって、どのように対応したら良いのか困ってしまいました。
普通は、その依頼を断ることを、「大勢の前で話すことから逃げる」と考える人がほとんどだと思います。
そして、「逃げる」ということを意識しているので、逃げないために、不安や嫌な気持ちを抱えながらも、「依頼を了解し大勢の前で話すべきではないか」という気持ちとの葛藤を経験するだろうと思います。
仮に、依頼を断ることによって、「人前で話す」ことから逃げることができたとしても、その後多くの場合、「依頼を了解し大勢の前で話せたらいいのに、自分はそれができずに断ってしまった」と自分を責めてしまい、やっぱり、嫌な気持ちを感じてしまうのではないかと思います。
この状況を違う角度から眺める為に、一度、次のように考えてみて下さい。
「逃げたい」と思う対象があるとき、恐らく100%の確率で、心には嫌な気持ちが生じていると思います。
そして、「逃げたい」と思うときの嫌な気持は、たぶん、物凄く不快な気持ちだろうと思います。
そんな気持ちをいつまでも感じ続けるのは、とても苦痛で耐えられないので、その不快な気持ちを感じないようになりたいと思うのは普通のことです。
そこで、『自分の中に生じた物凄く不快な気持ち』から逃げるために、『依頼を断る』という手段を使うのです。
ところが、依頼を断って課題から逃げたつもりになっていても、もう一つの気持ちが自分を責めてしまい、嫌な気持ちから逃れたはずなのに、別の嫌な気持ちを感じてしまいます。
つまり、逃げようとしても、『自分の気持ちからは、決して逃げることはできない』ということなのです。
俗に「逃げている」と認識されるときでも、自分に生じる嫌な気持ちからは逃れられずに向き合っているのですから、「逃げているかどうか」などということは考えなくても良いのです。
【まとめ】
『課題と向き合っているか?それとも、課題から逃げようとしているか?』ということは重要なことではありません。
『どのようにすれば、自分の気持ちと正しく向き合ったことになるのか?』ということこそが、私たちが取り組むべき命題なのです。
2. 「向き合う」ということ
「逃げる」ということに意識が集中し、それを問題視するようになってしまうと、その反対と思われる「逃げない(向き合う)」という対処を目標としがちなところがあります。
私たちが向き合うべき対象は、目の前の課題ではなく『自分自身の気持ち』だということは、前の章で説明しました。
これまでの文章を読んで、「自分の気持ちにきちんと向き合おうとしている」と感じる人は多いかもしれません。
しかし、多くの場合、不快を感じていない振りをしようとしていたり、不快な気持を打ち消そうとしていたりすることがほとんどではないかと思います。
はじめのうちはそれでごまかせていたかもしれませんが、自分の自然な気持ちを押し殺し続けるには限界があり、いずれ、自分が感じている苦しいという気持ちに直面せざるを得なくなります。
これは、『心が強い』とか『心が弱い』とかいう問題ではなく、恐らく全ての人に同じよう生じる自然な心の動きです。
でも、心に強い・弱いという違いがあるように感じることは確かにあります。
その違いは、なぜ、生じるのでしょうか?
それは、
■不快な気持ちを大丈夫にする方法があることを知っているかどうか
■その方法を、都度、きちんと実践しているかどうか
たった、それだけの違いなのです。
そして、そのことこそが、自分の気持ちと向き合うことにつながるのです。
その方法については、これまで何度も書いてきたつもりですので、今回は省略します。
【参考】
■そうかそうかムーブメント:
http://www.library.pureheart-counseling.com/single-content-collection/sokasoka/
■カウンセラーが理解した心:
http://www.library.pureheart-counseling.com/heart-by-counselor/
3.「解決する = 苦しい」という誤解
日本人は「乗り越えることは苦しいこと」という考えを感覚的に身につけてしまっているところがあるような気がしています。
逆に、苦しさを感じていないと、「乗り越えようとしている」と思えないと表現した方が分かり易いかもしれません。
しかし、前に説明したように、直面した課題は解決すれば良いのであって、別に「逃げる」「逃げない」「向き合う」「乗り越える」などということを考える必要はありません。
この辺りの感覚によって混乱してしまい、「解決することは、自分にとって好ましいこと」のはずなのに、「解決することは苦しいことだ」とか「苦しいと感じているってことは、解決しようとしているってことだ」とか「苦しくないのは良くないことだ」とかいうように錯覚してしまうのかもしれません。
4. 苦しみを好みがちになる背景
苦しさを乗り越えることを良しとするような感覚につながりそうな背景を、ちょっと想像してみようと思います。
【スポーツ根性論的経験】
もしかしたら、スポーツ根性論のようなところから来ているのかもしれません。
私が中学校・高校などでクラブ活動に取り組む時に
■苦しい練習を乗り越え、強い心に鍛え、それが成果につながる
なんてことを何となく教えられてきたような気がします。
そして、苦しさに耐えられない人は「根性が無い」と見下される雰囲気があったように思います。
【適応したときに評価される経験】
もう一つの可能性としては、教育の場の雰囲気です。受験を例にして説明してみます。
今の社会は、受験ということが前提の社会で、子供たちはその制約の中で目標を見つけるしかありません。
その目標と自分の本来の夢とを照らし合わせることを忘れずにいられる人もいますし、それを忘れて目指す学校の偏差値の高低と照らし合わせるという状況に陥ってしまう人もいます。このとき、前者の場合
■自分の欲しいもの(こと)を手に入れるために頑張る。
となるのですが、後者の場合は
■与えられた状況の中で、周囲から評価されることを自分の目標として置き換え、それを目指して肉体的・精神的な苦痛に耐える。
という状態になってしまっていると表現できるのかもしれません。
後者の状況に陥ってしまった場合、それを乗り越えれば、「偏差値の高い大学へ入学する」というような社会的には価値があるとされている成果が与えられるということは、肉体的・精神的苦痛に耐える理由としては十分なものなのかもしれません。
受験に限らず学校生活では、自分の価値観よりも教育現場の価値観が優先される傾向が強いと思います。
そして、その結果、受験の例で説明したことと同じように、苦しさを乗り越えれば、親・先生・社会に評価されるだろうということを期待するようになり、それを自分の本当に望んでいると錯覚してしまい、「苦しみ」から逃れられなくなる傾向につながるのかもしれません。
5.「楽」という言葉の意味
日本には、『楽をする』ことを良しとしない雰囲気もあるように思います。
『楽』という言葉には、「楽をする」というように「怠ける」というニアンスが含まれていることがあります。
これは、精神的な修行を大切にする日本独特の文化的背景によるのかもしれませんが、日本人は当たり前のこととしてに受け入れている感覚のような気がしています。
この雰囲気も、『心を楽にすることを避け、心が苦しいことを選ぼうとする』傾向を強める要因ではないかと思います。
6.まとめ
目の前の課題を解決するために、心が苦しいと感じていなければならないなんてことはありません。
楽に解決することに越したことはないのですから。
そう考えて改めて振り返ってみると、これまで「こんなことは解決したことにはならない」と思っていた多くのことを、「自分がきちんと解決してきたこと」として認めてあげられそうな気がしませんか?
楽に課題を解決していたら、それは、素晴らしいことなのです。
そして、今まで困難だと感じていた課題も、それと同じように楽に解決できる方法を探せば良いのです。
その為には、「課題を苦しんで解決したら心が強くなる」なんて考えずに、とにもかくにも、まずは、心を楽にしてあげる事が大切です。
その結果、心が楽になるから、乗り越えるなんてことは考えなくても良くなり、純粋に課題を解決しようと取り組めるようになるのです。
また、心が楽になるということを知っているから、多少苦しくなりそうなことにでも、「ちょっと取り組んでみようか」という気持になれるのです。
メルマガ編集後記【No.0012】
今回のメルマガは、かなり長文になってしまいました。
(バックナンバー:メルマガ「読むカウンセリング」(No.0012) 『楽』になっても良いんです)
各章の論理的なつながりは、うまくできていないかもしれませんが、読み終わったあと、心の中で各章の内容が何となく結びついて、ぼんやりと何かを感じて頂けることを願っています。
メルマガでは、「どっちにしても、『自分の中の嫌な気持ち』からは逃げられない」という論調で説明しました。
でも、正確に表現すると、『本当の気持ちから逃げられない』ということです。
本当の気持ち、そこには様々な感情(嬉しい、悲しい、寂しい、楽しい、つらい、苦しい・・・)が含まれます。メルマガではそんな感情に絞って説明したわけですが、そこには、自分の本当の望みも含まれています。
メルマガの例で言えば、「大勢の前で話す」ということに、何の興味も無いのなら、大勢の前で話そうが話すまいが、別に、どっちでも良いことです。
話さなくても、自分の気持ちは、サッパリしたものです。
しかし、そこに「大勢の前で話してみたい・・・」という望みが、例え僅かでもあるのなら、その自分の望みを大切に思い、それを叶えていこうとするということも、自分の気持ちから逃げないことになります。
そんな時、自分の中に生じたネガティブな感情や感覚を、自分自身が優しく受けとめ癒やすことができれば、きっと、願いを大切にし続けることにつながるだろうと思います。
結局のところ、私たちが『逃げる』ということを意識した時に
■目の前の課題から逃げる
と思っていたことは、直接の動機としては
■嫌な気持ちから逃げる
ということではあるのですが、その構図を全体を眺めた時に
■自分の願いから逃げる
ということになっているのだろうと思います。
そんな構造的なところからで身に着いた習慣や感覚によって、『心が楽になる』という一番手に入れたいことの実現を目前にすると、そこから逃げたくなる感じが生じてしまうのかもしれません。
「楽になるって、逃げることにはなりませんか?」という質問の意味は、そういうことではないかと思います。
願いが叶っても良いんです!
願いが叶う事に臆病にならず、次々に、願いを叶えていきましょう!
例えば、「いつか、きっと、海外旅行をしよう」と夢見ているとしたら、とりあえず言ってしまえば良いのです。
その気になれば、案外、簡単に実現することは多いということが体験で理解できると思います。